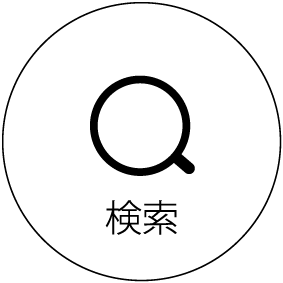2週間に1件起きている介護殺人。長寿大国日本、でも寝たきり老人は欧米の10倍。

幼い子供に対して「もうお兄ちゃん(お姉ちゃん)でしょ?」という言葉をかけると自発的に後片付けをするようになる一方で、高齢者に対して「もうおじいちゃん(おばあちゃん)なんだから」という言葉をかけると脱力感に襲われ、周りに頼る機会が増えてしまうように、年をとったという無力感を生み出すものは周囲の環境だと言えるのではないでしょうか。
そういった環境から生まれる年齢に対する思い込みや心の持ちようが、良くも悪くもその人の脳の働きや行動を大きく左右するということは、ハーバード大学で心理学を専門とするエレン・ランガー教授によって行われた実験によって、すでに1979年の時点で明らかになっています。
目次-contents-
自分に繰り返し向けられる言葉が、脳や体の働きをコントロールしていく

ランガー教授の実験では75歳から80歳の被験者を田舎の合宿所に集め、彼らが50代半ば以降に撮った写真やそれ以降に書かれた本などは持ち込めないようにし、そこでは20年前の自分に戻ったつもりで話をするように促されるなどして、実質的に高齢の被験者たちは50代半ば以前に戻ったような気持ちで生活を送りました。(1)
その様子を観察をしていると、面接の時は連れてきてくれた家族にすっかり頼りきりだった被験者たちが、合宿所に到着したその日から食事の準備や片付けに積極的に関わるようになり、聴力、記憶力、そして握力が彼らが50歳の時とほとんど同じくらいの基準にまで向上したといいます。(2)

↑20年前と同じ環境に身を置くことで実際に20歳も若返った
実験を通じて体と心には強い繋がりがあると確信したエレン・ランガー教授でしたが、そもそも参加者たちが弱っていた原因はプログラムの参加者の娘や息子などの家族にあったそうで、例えば、実験を行う前の面接で、彼らの家族はどこか見下すような感じで自分たちの両親について次のように語っていたと言います。(3)
「父は昔と違って今は何に対してもやる気を見せないんです。目も悪いですから本も読まなくなったし、体力が落ちてゴルフもできない。それにどんなに厚着をしてもすぐに風邪をひくし、何を食べても美味しくないと言う。灰色の人生ですよ、まったく。」
このように、年齢を重ねていくごとに脳や体は衰えて当然だというのは多くの人の思い込みで、このプログラムで参加者たちが若返ったように、必ずしも歳をとったから衰えるわけではありませんし、「年寄りは何もできない」という思い込みに囚われていた家族こそが、高齢者に自立した生活を送れなくさせる根本的な原因だったのです。

↑参加者たちの無力感や脱力感の原因は彼らの家族だった
私たちが生まれてから初めて接する高齢者といえば、祖父母の場合がほとんどで、両親が彼らに対して「もう年なんだから無理しないでよ」と声かけをしている状況を見ながら育った私たちは、「高齢者=何もできない人」と無意識のうちに高齢者に対してネガティブなイメージを持つようになったのかもしれません。
このような自分自身の周りの世界に対する理解や判断の基準となるものは「フレーム・オブ・レファレンス」と呼ばれており、アップルの創業者、スティーブ・ジョブズはあるインタビューの中で、この社会に生きる多くの人が偏見に囚われ多くの場面において間違った判断をする傾向があるとして、次のように述べています。
「私たちの社会に存在する偏見や常識というものは、あまり賢くない人たちによって作り出されたものだという事をほとんどの人が理解していないし、それに従うのが当然だと思い込んでいる。完全にイカれてるよ。」
無意識のうちに高齢者は「何もできない」と勝手な判断基準を自分の中に作ってしまう

例えば、若い人たちが高齢者に対して持っている偏見の中に「脳細胞は1日10万個死ぬから、高齢者ほど脳の機能が低い」というものがありますが、最新の研究によると100歳の老人と20歳前後の若者とでは脳細胞数はほとんど変わらないという事が分かってきていることから、脳の機能は脳細胞の数によって決まるものではないという事がわかります。(4)
そのため、年老いた両親が「最近、物忘れが多くてね」と心配しているレベルにおいては、その原因は脳細胞の「数」の減少ではなく、「質」の低下が問題だと考えらていて、質が低下している状態は植物で言えば、水や養分が足りずに萎れているだけのため、脳のおかれた環境を変えたり、トレーニングをする事で回復する事ができるそうです。(5)

↑100歳の老人と20歳前後の若者とでは脳細胞数はほとんど変わらない、問題は量ではなく「質」(リンク)
年齢別の人口比率を見たときに65歳以上の高齢者が占める割合が全国で4番目に高い熊本市では、2006年に「おとなの学校」という学校形式のデイサービスがスタートしました。10年経った現在、フランチャイズ化され全国展開しているこの学校は、国語や算数、社会、そして家庭科などの「授業」によって脳のリハビリを行うもので、通ってくる生徒は要介護の高齢者のみならず、認知症と診断されている人も多くいます。
たとえば社会科の授業では「もみじまんじゅう」や「ずんだ餅」などの名産品の写真を教材に、生徒がその名前を答えたり、旅行の思い出について語り合う内容などがありますが、記憶が引き出されることは脳によい刺激となり認知症の生徒の徘徊がおさまるといったリハビリ効果が見受けられるのだそうで、授業を受けている83歳を迎えたある女性も「ああ、こんなこともあったなあ」と記憶を辿ることを楽しいと感じていると話しました。
本当に認知症患者の安全を守るのは、薬や監視ではなく脳のリハビリなのかもしれない

欧米諸国の10倍近い数の寝たきり高齢者がいるという日本で、デイサービスの市場は今後10年で少なくとも1.5倍は拡大するといわれる中、これから特に高齢者の自立を助ける上で欠かせない存在となってくるのは、「リハビリ・デイサービス」と呼ばれる種類の、ジムのようなトレーニング器具のある高齢者向けの施設と言われています。
2013年に放映されたABC朝日放送「日本のちから」の第7話に登場したリハコンテンツ株式会社は、そういったリハビリ施設の先駆けとなった企業であり、社長の山下哲司氏はリハビリを提供するというよりも高齢者が体が弱ってしまうことなどで失っていくプライドを取り戻す「プライドメーカー」になるのだとして、高齢者がリハビリに通うことで変化していく様子を次のように語りました。
「運動機能を改善するだけではなくて、姿かたちもどんどん変わってこられるんですね。かっこいいTシャツを毎日着てこられるようになったり。女性の方ですと、きちんとお化粧をしてこられるようになったり。」

↑傍目に見えるよりも、トレーニングを受ける本人の中では確実に大きな変化が始まっている
こうした高齢化が進んだ社会だからこその自立支援が始まっているにもかかわらず、即老人ホームに入ることになった高齢者のよくあるケースは、ちょっとしたことで周囲の人に「無理をするな」「できっこない」というレッテルを貼られてしまった結果なのかもしれません。
たとえば、あるおばあさんが買い物に行ってきた後の日常的な行動のプロセスは、まずハンドバッグからドアの鍵を取り出すために買い物袋を玄関の前の地面に置き、取り出した鍵を使ってドアを開け、かがんで下に置いた買い物袋を持ち上げて家の中に入るというようになっていましたが、ある日突然腰が曲がらなくなってしまったために下に置いた買い物袋を取ることができなくなってしまいます。その日は偶然、近所の人が通りかかって助けてくれましたが、家族から「無理しないでよ」と言われてしまい、落ち込んでいたおばあさんを心配した娘が老人ホームに入れる手続きをしてしまうのです。(6)
しかし、ドアの外におばあさんが帰ってきたときに買い物袋を置ける棚を設置すれば、おばあさんは普段通りに自立した生活を続けることができていましたし、そもそも人が年をとり体が変化すれば、その人が住む家も当然変化する必要があるにも関わらず、多くの人はそれを家の問題とせずに片付けてしまいます。

↑人が変化しているのに、その人の住む家が変化しないのはどう考えても不自然
あまりにも当たり前のことですが、25歳の男性が子供用の三輪車に乗るのに苦労するのは、ただ単にその三輪車が幼稚園児が乗ることを想定して作られており、25歳の男性が乗るようには設計されていないため、三輪車にうまく乗る事ができない25歳の男性を無能だとみなす人は誰もいません。
一方で、高齢者の能力を評価するときになると、「道具は使う人に合わせて設計されるべきだ」という原則が忘れ去られ、それを使うことができない高齢者の方に問題があるというふうに捉えられてしまいます。高齢者は毎日、若い人向けに設計された世界の中で生活することを強いられているのですから、少し発想を変えて、人を環境に合わせるのではなく、環境を人に合わせるようにすれば高齢者が気持ちよく生活できるのではないでしょうか。(7)
高齢者が“若者向け”に設計された世界で苦しみながら生活している事に誰も気づいていない

近年、段差などを無くすバリアフリーが至る所で見られる一方で、それとは対照的に、あえて段差や階段を設けたりすることで高齢者に自立した生活を促す「バリアアリー」という試みが注目を集めているようです。
東京都世田谷区の介護施設、夢のみずうみ新樹苑では単なる老人ホームではなく「自分ができることの再発見の場」を提供していて、その取り組みの一つに「One Step One Goods」と呼ばれるものがあり、それは施設内にあえて段差や長い廊下を設置するのと同時に、自立した食事や移動などを促すために必ず一歩先に掴むもの、すがるもの、寄りかかるものを設置しています。
そうすることで、バリアフリーのように高齢者から全てを取り上げることなく、彼らが快適に生活できるように環境を人に合わせることができますし、この取り組みであれば家庭でも真似をすることは十分に可能であるため、試してみる価値はあるのではないでしょうか。
高齢者にとって必要なものは何でもやってくれる介護スタッフではない

今まで掃除、洗濯、料理に買い物など全て自分でこなしていた元気なおばあさんが、あるキッカケで老人ホームに入って足を動かさなくなると、あっという間にアルツハイマー病を患い、あっけなく亡くなってしまうという事が最近よくありますが、その人を「年寄り」という枠にはめ、老人ホームに入居させるという今の社会の流れは高齢化社会をどんどん暗くさせているのかもしれません。
実際、60代後半にもなると、多くの人は自分が生きていることが人の迷惑にならないようにするにはどうすればいいのかという不安にとらわれていくようになり、昨今では、将来を悲観した高齢の夫婦が「老老介護」の末に無理心中してしまうという例が珍しくなく、介護の苦悩によって2週間に1人の割合で殺人事件が起きているそうです。
「人に迷惑をかける」か「介護殺人」の二択しか選択肢が見えない

結婚という形式にこだわらずカップルよりも個人を優先するフランスでは、NPOや企業が仲介となって高齢者と学生が家をシェアする「世代間同居」という取り組みが広まっており、その数は2012年時点で1000組を超え、調査を受けた同居者の95パーセントが状況に満足しているといいます。
ルールとして、ただ家賃を浮かせるつもりの学生も、ただヘルパーに一緒に住んでほしいという高齢者も、この取り組みからは除外され、あくまで対等な人間同士の同居を守っていることは特に見逃せないポイントでしょう。
フランス人で国際ジャーナリストのドラ・トーザン氏は、フランス人のような年齢など関係なくずっと自分らしさを探し続けている人生は、「独身→結婚→家族」の順番をなぞることよりも快適な生き方なのではないかと、著書「パリジェンヌ流今を楽しむ!自分革命」の中で私たちに語りかけてきます。(8)
「ひとりで生きることは若さを延ばす効果もあります。だって型通りの人生プランなどは関係なく、未来をいつまでも夢見ることができるのだから。」
ひとりの人間として生きる人生に引退はない

本当の意味で高齢者が必要としているものは家政婦さんのような介護スタッフではなく、プライドを取り戻すためのきっかけと、住環境を高齢者に合わせて暮らしを補助するほんの少しの工夫だけなのではないでしょうか。
健康で豊かな人生を送るためにも、まずは「老い」に対する間違った認識を捨て去り、自分らしく過ごせる生活環境や人とのつながりを整えることで、おのずと健康寿命は延びていくものなのです。
- 参考資料
- マーシャ・キャノン「プロカウンセラーが教える「怒り」を整理する技術」(2013年 日本実業出版社)p97
- エレン・ランガー「ハーバード大学教授が語る「老い」に負けない生き方」(2011年 アスペクト)p22
- エレン・ランガー「ハーバード大学教授が語る「老い」に負けない生き方」(2011年 アスペクト)p14
- 久恒 辰博「大人にもできる脳細胞の増やし方」(2007年 角川書店)p17,49
- 久恒 辰博「大人にもできる脳細胞の増やし方」(2007年 角川書店)p22
- エレン・ランガー「ハーバード大学教授が語る「老い」に負けない生き方」(2011年 アスペクト)p95
- エレン・ランガー「ハーバード大学教授が語る「老い」に負けない生き方」(2011年 アスペクト)p177
- ドラ・トーザン「パリジェンヌ流 今を楽しむ! 自分革命」(2012年 河出書房新社)Kindle